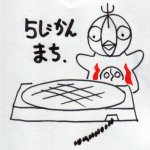 博覧会の魅力の一つに、多彩なパビリオンがあります。
大阪万博では、そのパビリオンの多彩さから、
「建築オリンピック」とも言われていました。
ガスパビリオンのデザインは、豚の蚊取り線香の置物にそっくりな、
ユーモラスな顔つきのパビリオン。
館内の冷暖房、照明までも全てガス、会場が停電してもガスパビリオンは
大丈夫と言われていました。
博覧会の魅力の一つに、多彩なパビリオンがあります。
大阪万博では、そのパビリオンの多彩さから、
「建築オリンピック」とも言われていました。
ガスパビリオンのデザインは、豚の蚊取り線香の置物にそっくりな、
ユーモラスな顔つきのパビリオン。
館内の冷暖房、照明までも全てガス、会場が停電してもガスパビリオンは
大丈夫と言われていました。
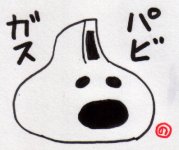 タカラビューティリオンは、一辺、3.3m×3.3mの立体格子に、
いろんな部屋のユニットを組み合わせた、ユニット工法。
現在のプレハブ建築工法の元祖です。
スイス館は、32,000個もの電球を使った、光の樹。
夜は綺麗なのですが、昼間は・・・。
上空から見ると、大阪万博のシンボルマーク、桜の形は日本館。
このデザインの推進者は、当時、通産省のキャリアだった池口小太郎氏。
現在(2000年4月)の経済企画庁長官で作家の堺屋太一氏です。
日本館の敷地面積は、約37,791平方メートルで、
さすが主催国、面積はNo.1でした。
また、この敷地面積が日本の国土の約1000万分の1とのことが、
当時の万博ガイドなどには、豆知識としてありました。
いかにも、日本的な「小ネタ」ですね。
タカラビューティリオンは、一辺、3.3m×3.3mの立体格子に、
いろんな部屋のユニットを組み合わせた、ユニット工法。
現在のプレハブ建築工法の元祖です。
スイス館は、32,000個もの電球を使った、光の樹。
夜は綺麗なのですが、昼間は・・・。
上空から見ると、大阪万博のシンボルマーク、桜の形は日本館。
このデザインの推進者は、当時、通産省のキャリアだった池口小太郎氏。
現在(2000年4月)の経済企画庁長官で作家の堺屋太一氏です。
日本館の敷地面積は、約37,791平方メートルで、
さすが主催国、面積はNo.1でした。
また、この敷地面積が日本の国土の約1000万分の1とのことが、
当時の万博ガイドなどには、豆知識としてありました。
いかにも、日本的な「小ネタ」ですね。
 1970年当時、まだ、アメリカと旧ソ連の2大国は、冷戦状態にあり、
大阪万博でも、その2国のパビリオンは異彩を放っていました。
高さがNo.1のソ連館(108m)に対して、
アメリカ館は高さこそ低いものの、ソ連館とは違う特色で、
関心を集めていました。
それは、柱を一本も使っていない、エアドームだったのです。
長径142メートル、短径83.5メートルの楕円形で、
白いガラス繊維膜で出来た屋根を空気で支える。
アメリカ館内の、宇宙関連の展示と相まって、
それは、まるで月面に建つ、宇宙基地の様相でした。
そして、大阪万博から18年後の、1988年。
東京は水道橋に、アメリカ館そっくりの建物が出現しました。
その名は「東京ドーム」。
日本初の全天候型多目的ドーム球場である「東京ドーム」は、
1988年3月17日オープン。
建築面積は、アメリカ館を遙かにしのぐ、46,755平方メートル。
最高部の高さは、56.190メートル有り、
その容量は、約124万立方メートルと、かなり大きなモノです。
天井は、アメリカ館と同じ、ガラス繊維膜。
(但し、東京ドームのものは、東京ドーム用に開発された特製。)
内部の気圧を、外部より0.3%高くし、屋根を支えています。
1988年、夏。
私はどうしても、東京ドームが見たくなって、友人を誘って、
東京へ遊びに行きました。
その時は、都市対抗野球の真っ最中だったのですが、
内野席に座り、天井を見上げたとき、
ガラス繊維膜から漏れる、夏の光の白が、
アメリカ館の白と重なって、何とも言えぬ気分になりました。
その後、福岡ドーム、名古屋ドーム、大阪ドーム、西武ドームと
ドーム球場が出来ましたが、現時点でエアドームは東京ドームだけです。
やはり、エアドームは維持費が掛かるのか、それとも建築コストの問題か、
アメリカ館の弟分は、今のところたった一人です。
ガラス繊維膜越しに光を感じるエアドーム。
あの光の色に、未来の宇宙基地を予感させる不思議な感覚が好きなのですが。
1970年当時、まだ、アメリカと旧ソ連の2大国は、冷戦状態にあり、
大阪万博でも、その2国のパビリオンは異彩を放っていました。
高さがNo.1のソ連館(108m)に対して、
アメリカ館は高さこそ低いものの、ソ連館とは違う特色で、
関心を集めていました。
それは、柱を一本も使っていない、エアドームだったのです。
長径142メートル、短径83.5メートルの楕円形で、
白いガラス繊維膜で出来た屋根を空気で支える。
アメリカ館内の、宇宙関連の展示と相まって、
それは、まるで月面に建つ、宇宙基地の様相でした。
そして、大阪万博から18年後の、1988年。
東京は水道橋に、アメリカ館そっくりの建物が出現しました。
その名は「東京ドーム」。
日本初の全天候型多目的ドーム球場である「東京ドーム」は、
1988年3月17日オープン。
建築面積は、アメリカ館を遙かにしのぐ、46,755平方メートル。
最高部の高さは、56.190メートル有り、
その容量は、約124万立方メートルと、かなり大きなモノです。
天井は、アメリカ館と同じ、ガラス繊維膜。
(但し、東京ドームのものは、東京ドーム用に開発された特製。)
内部の気圧を、外部より0.3%高くし、屋根を支えています。
1988年、夏。
私はどうしても、東京ドームが見たくなって、友人を誘って、
東京へ遊びに行きました。
その時は、都市対抗野球の真っ最中だったのですが、
内野席に座り、天井を見上げたとき、
ガラス繊維膜から漏れる、夏の光の白が、
アメリカ館の白と重なって、何とも言えぬ気分になりました。
その後、福岡ドーム、名古屋ドーム、大阪ドーム、西武ドームと
ドーム球場が出来ましたが、現時点でエアドームは東京ドームだけです。
やはり、エアドームは維持費が掛かるのか、それとも建築コストの問題か、
アメリカ館の弟分は、今のところたった一人です。
ガラス繊維膜越しに光を感じるエアドーム。
あの光の色に、未来の宇宙基地を予感させる不思議な感覚が好きなのですが。
エアドームは好きですが、フランチャイズにしている球団が 好きなわけではありません。あしからず。 1988年に東京ドームで買った「東京ドームしおり」。 本に挟むしおりなのですが、 素材が東京ドームの屋根と同じガラス繊維膜で出来ていてとても丈夫です。 12年間、ずっと使っていますが、汚れないし、折れない。 優れモノ、おすすめグッズです。 「エアドーム」 実現度・・・・・★★★★★ 快適度・・・・・★★★★★ 虎応援度・・・・★★★★★ 『関連サイト』 東京ドーム http://www.tokyo-dome.co.jp/
